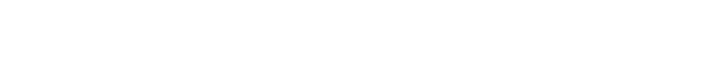脳卒中
こんにちは、院長の山須田です。
当院で高血圧治療をする目的の一つに脳卒中予防が挙げられます。ここでは、脳卒中について概要を説明いたします。
脳卒中とは
脳卒中とは、脳の血管が破裂したり詰まったりする疾患の総称です。
脳卒中は大きく①脳出血(脳実質内出血、くも膜下出血)と②脳梗塞(心原性脳塞栓症、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、その他の脳梗塞)に大別されます。
脳卒中のリスク因子として、高血圧、脂質異常症、糖代謝異常(糖尿病)、心房細動、肥満・メタボリックシンドローム、睡眠時無呼吸症候群、喫煙などが挙げられます。特に高血圧は最大の要因です。
医学の進歩等に伴い死亡率は減少傾向ですが、後遺症によるQOL低下は依然深刻です。生活習慣の改善および必要に応じて内服治療を行い、発症を予防することが大切です。
| 脳卒中予防のための降圧目標 | |
| 130/80mmHg未満 | 75歳未満 冠動脈疾患 CKD(尿蛋白陽性) 糖尿病 抗血栓薬服用中 |
| 140/90mmHg未満 | 75歳以上 両側頸動脈狭窄・主幹動脈閉塞あり CKD(蛋白尿陰性) |
脳梗塞の概要
脳血管障害で最も多い疾患で、中年~高齢者に見られます。
閉塞する動脈の部位により、①ラクナ梗塞 ②アテローム血栓性脳梗塞 ③心原性脳塞栓症 ④その他の脳梗塞 に分類されます。
また、一過性(24時間以内に消失)の脳血管障害をTIA(一過性脳虚血性発作)といいます。
①ラクナ梗塞…脳の主幹動脈から分岐して大脳基底核など脳深部へ向かう穿通枝(細い血管)の閉塞。
②アテローム血栓性脳梗塞…動脈硬化(プラーク)が原因で脳血管が狭窄し、血栓性または塞栓性に閉塞する。
③心原性脳塞栓症…心不全や心房細動などが原因で心腔内に血栓が生じ、脳に飛んで主幹動脈を閉塞する。
脳梗塞の初期症状を認めた場合、すぐに救急要請し可能な限り早く治療を開始、脳血流を再開することが求められます。
脳梗塞の症状・検査・診断
主な症状は神経症状(意識レベル低下、運動・感覚障害)です。
初期症状はFAST(Face顔の麻痺, Arm片腕に力が入らない, Speech呂律障害、言葉が出ない, Time発症時刻)で脳梗塞が疑われた場合は直ちに救急要請し、病院を受診します。
診断にはCT・MRI評価が必要です。
重症度評価にはNIHSS(米国立衛生研究所脳卒中スケール)を用います。
TIA発症時の脳梗塞発症リスク評価には、ABCD2スコアを用います。
| ABCD2スコア | ||
| A | Age | 60歳以上=1点 |
| B | Blood Pressure | 140/90mmHg以上=1点 |
| C | Clinical Features | 半身麻痺=2点、麻痺のない言語障害=1点 |
| D | Duration | 60分以上=2点、10~59分=1点 |
| D | Diabetes | 糖尿病=1点 |
| 合計 | ||
0~3点:低リスク(7日以内脳梗塞発症0.6%)
4~5点:中リスク(7日以内脳梗塞発症2.5%)
6~7点:高いリスク(7日以内脳梗塞発症4.3%)
脳梗塞の急性期治療
①全身管理
脳梗塞急性期の高血圧に対しては降圧せずそのまま様子を見ますが、①220/120mmHg以上が持続する場合 ②大動脈解離・急性心筋梗塞・心不全・腎不全などを合併している場合は降圧を考慮します。
また、rt-PA予定で185/110mmHg以上、rt-PA後24時間以内で180/105mmHg以上の場合は降圧療法を行います。
低血圧に対しては輸液、昇圧剤を使用し是正します。
DVT予防には、早期離床、理学療法、間欠的空気圧迫法などを行います。
②経静脈的血栓溶解療法
発症から4.5時間以内またはその可能性がある場合、rt-PA(アルテプラーゼ)投与による治療を行います。アルテプラーゼはプラスミン活性化促進によりフィブリンを溶かします。
脳血流再開とともに脳出血を誘発するリスクがあり、適応基準を満たした症例のみが治療対象です。
③血栓回収療法
カテーテルにより血栓を直接除去する治療です。
適応は「(1)内頚動脈または中大脳動脈M1の急性閉塞(2)mRSスコア0または1(3)頭部CTまたはMRI拡散強調画像でASPECTSが6点以上(4)NIHSSスコア6点以上(5)年齢18歳以上」の(1)~(5)すべてを満たし、rt-PAに追加して発症から6時間以内の症例に対して行います(6時間を超えた症例に対しても、神経徴候および画像診断に基づいて症例選択したうえで実施します)。
④急性期抗血栓療法
抗血栓療法の薬には、抗血小板薬と抗凝固薬があります。脳梗塞の発症機序により使い分けます(非心原性と心原性両方ある場合、抗凝固薬を優先)。
・非心原性脳塞栓症(ラクナ梗塞やアテローム血栓性脳梗塞など)
抗血小板薬を用います。アスピリン160~300mg/日単剤投与を基本に、短期間に限り(1か月程度)DAPT(アスピリン+クロピドグレル)を考慮します。
発症5日以内はオザグレルナトリウム160mg/日点滴を考慮します。
・心原性脳塞栓症
抗凝固薬(DOAC, ワルファリン)を用います。
DOAC開始は1-3-6-12dayルール(TIAは発症翌日、軽症(NIHSS<8)脳梗塞は発症から3日後以降、中等症(8≦NIHSS<15)脳梗塞は発症から6~8日後以降、重症(16≦NIHSS)脳梗塞は発症から12~14日後以降に開始)を参考に、早期から開始します。
⑤エダラボン
腎障害がなければ、発症24時間以内の脳梗塞に1週間程度用います。
エダラボンはフリーラジカルスカベンジャーで、神経細胞の壊死を抑えることで梗塞が広がるのを防ぐ作用(脳保護作用)があります。
⑥急性期リハビリテーション
できるだけ早急に離床、リハビリテーションを行います。
脳梗塞の慢性期治療(再発予防)
抗血栓療法を継続し、その上で高血圧・糖尿病・脂質異常症の治療、および禁煙・節酒等による生活習慣の改善を行います。
・非心原性脳塞栓症(ラクナ梗塞やアテローム血栓性脳梗塞など)
抗血小板薬(アスピリン75-150mg/日、クロピドグレル75mg/日、シロスタゾール200mg/日)のいずれかを副作用を考慮して選択します。
DAPT(抗血小板薬2剤併用)は出血リスクが高く通常は行いませんが、頸部/頭蓋内動脈狭窄や血管危険因子を複数有する場合はDAPT(シロスタゾール+他剤)を行います。
・心原性脳塞栓症の原因となる非弁膜症性心房細動(NVAF)にはDOACを第一選択とします。
ただし、機械弁置換術後、心房細動を伴うリウマチ性僧帽弁狭窄症ではワルファリンを使用します。
脳出血の概要
大きく①脳(実質内)出血②くも膜下出血に分類されます。
脳出血は脳内の血管壁が破れて出血をおこす疾患です。高血圧や高齢によるアミロイドアンギオパチーが主な原因となります。
出血部位により被殻出血・視床出血・脳幹出血・小脳出血・皮質下出血に分類されます。
くも膜下出血は、脳を覆っているくも膜に出血を来たす疾患です。頭部打撲や交通事故などの外傷性くも膜下出血と、脳動脈瘤破裂・脳動静脈奇形・もやもや病などに起因する非外傷性くも膜下出血に分類されます。
脳出血の症状・検査・診断
主な症状は脳梗塞と同じ神経症状です。
脳梗塞と比較すると、頭痛・悪心・嘔吐の頻度が高く、前兆がなく突然発症することや、短時間で症状が進行することが多いです。特にくも膜下出血の場合は「バットやハンマーで殴られたような」突然おこる激しい頭痛が特徴です。
直ちに救急搬送、CT・MRI評価が必要となります。
脳出血の治療
①全身管理
気道確保(挿管)、鎮静、酸素投与を行います。血圧は収縮期140mmHgまで降圧し7日間維持します。
適宜、鎮痙剤(フェニトイン等)・抗胃潰瘍薬・抗血栓療法に対する中和剤・抗脳浮腫薬(マンニトール・グリセオール)・止血剤(トラネキサム酸)を投与します。
②外科的治療
脳出血に対して、開頭血腫除去術、内視鏡的血腫除去術、脳室ドレナージ術を行います。
くも膜下出血に対しては、開頭脳動脈瘤クリッピング術または脳動脈瘤コイル塞栓術を行います。
参考文献
脳卒中ガイドライン2021
日本脳卒中学会HP
参考資料:脳卒中に関する近年の論文紹介
・Tenecteplase for Ischemic Stroke at 4.5 to 24 Hours without Thrombectomy
N Engl J Med 2024 Jul 18;391(3):203-212
血栓除去術なしでの脳梗塞発症後4.5~24時間におけるテネクテプラーゼの有効性に関する第3相RCT(TRACEⅢ)。血栓除去術を受けられない中大脳動脈または内頚動脈閉塞があり発症4.5~24時間以内の患者に対し、テネクテプラーゼ0.25mg/kg投与群と標準的薬物療法群に無作為に割り付け比較。90日後の障害のない(mRS0/1)患者はテネクテプラーゼ投与群33%標準的薬物療法群24.2%でテネクテプラーゼ投与群が有意に高かった。90日死亡率はそれぞれ13.3%、13.1%と有意差がなかった。一方、治療後36時間以内での頭蓋内出血発生はそれぞれ3.0%、0.8%であった。
・Symptomatic Intracranial Hemorrhage With Tenecteplase vs Alteplase in Patients With Acute Ischemic Stroke: The Comparative Effectiveness of Routine Tenecteplase vs Alteplase in Acute Ischemic Stroke (CERTAIN) Collaboration
JAMA Neurol 2023 Jul 1;80(7):732-738.
アルテプラーゼとテネクテプラーゼの投与後頭蓋内出血リスクを比較した研究。頭蓋内出血発症率はテネクテプラーゼ群1.8%アルテプラーゼ群3.6%で、テネクテプラーゼ群で低かった。
・Dual Antiplatelet Therapy With Cilostazol for Secondary Prevention in Lacunar Stroke: Subanalysis of the CSPS.com Trial
Stroke 2023 Mar;54(3):697-705.
ラクナ梗塞における長期DAPTの有効性を検証したRCT。ラクナ梗塞に対してSAPT(アスピリンまたはクロピドグレル単剤)群、DAPT(シロスタゾール+アスピリン、またはシロスタゾール+クロピドグレル)群で0.5~3.5年追跡調査したところ、脳梗塞再発はSAPT、DAPTでそれぞれ461人中31人、464人中12人とDAPTの方が有意に低かった。安全面では、重篤な出血の発生率は両群間で有意差がなかった。
・Practical “1-2-3-4-Day” Rule for Starting Direct Oral Anticoagulants After Ischemic Stroke With Atrial Fibrillation: Combined Hospital-Based Cohort Study
Stroke 2022 May;53(5):1540-1549.
非弁膜症性心房細動の脳梗塞またはTIA後のDOAC開始に関する「1-3-6-12日ルール」より早期から開始することに関しての研究。TIA、軽症(NIHSS0~7点)、中等症(8~15点)、重症(16点~)において早期治療群(1-2-3-4日)と後期治療群を比較したところ、早期治療群の方が発症90日までの脳卒中・塞栓症が有意に少なく、大出血に群間差はみられなかった。
・Dual Antiplatelet Therapy vs Alteplase for Patients With Minor Nondisabling Acute Ischemic Stroke: The ARAMIS Randomized Clinical Trial
JAMA 2023 Jun 27;329(24):2135-2144.
軽度脳梗塞(NIHSS5点以下かつ主要な単一のスコア1点以下)におけるDAPTと血栓溶解療法を比較したRCT。発症後4.5時間以内にDAPT(クロピドグレル+アスピリン)投与した群とアルテプラーゼ投与群で比較したところ、90日目までのmRS0/1と神経学的に経過良好だった割合はそれぞれ93.8%、91.4%であり、DAPTがアルテプラーゼ投与に対して非劣性を示した。また、90日目までの頭蓋内出血はそれぞれ0.3%、0.9%であった。
・Allogeneic Stem Cell Therapy for Acute Ischemic Stroke: The Phase 2/3 TREASURE Randomized Clinical Trial
JAMA Neurol. 2024 Feb 1;81(2):154-162
発症から18~36時間の脳梗塞急性期(NIHSSスコア8~20点、梗塞が長径2cm超)に対する幹細胞(MultiStem)治療に関する第2/3相RCT。90日目のmRS0/1と神経学的に経過良好だった割合は、MultiStem治療群とプラセボ群でそれぞれ11.5%、9.8%で有意差はなかった。安全性に関しても、両者間に有意差はなかった。