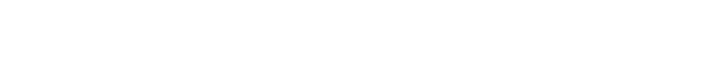第2章 科学的なダイエットの基本原則|太りにくい体を作る
こんにちは、高血圧といびきの内科 神保町駅前の理事長の鎌形博展です。
神保町院では院長の山須田医師が、毎日多くの患者さんの体重管理をサポートしています。
「先生、本当に効く痩せ方を教えてください。いろいろ試したのに、全然続かないんです…」
こんな悩みをよく伺います。テレビや雑誌、SNSでは様々なダイエット法が紹介されていますが、どれが本当に効果的で、自分に合っているのか判断するのは難しいものです。
実は、効果的なダイエットには共通する科学的原則があります。「極端な食事制限」や「特定の食品だけを食べる」といった方法は一時的に体重が減っても長続きせず、多くの場合リバウンドしてしまいます。
この章では、医学的に効果が証明されている減量の基本原則をお伝えします。これらの原則をしっかり理解し、自分の生活に無理なく取り入れることで、健康的で持続可能な減量が可能になります。
2章の内容
- カロリー制限と糖質制限の科学的比較
- 健康的な減量に必要な栄養素バランス
- 時間制限食・間欠的断食の可能性
- 食習慣の効果的な見直し方
- 太りにくい体を作る食事のタイミング
カロリー制限と糖質制限の科学的比較
「カロリー制限と糖質制限、どちらが効果的なのでしょうか?」
これは診察室でよく受ける質問です。近年、糖質制限が注目されていますが、従来のカロリー制限も多くの研究で効果が確認されています。それぞれの特徴を科学的な視点から比較してみましょう。
減量の基本原理:エネルギー収支
まず基本中の基本として、体重減少はエネルギー収支が負(摂取カロリー<消費カロリー)の状態が続くことで起こります。つまり、摂取するエネルギーより消費するエネルギーが多い状態を作る必要があるのです。
カロリー制限も糖質制限も、この原理に基づいていますが、アプローチが異なります。
カロリー制限の仕組みと特徴
カロリー制限は、1日の総摂取カロリー量を制限する方法です。
- 科学的根拠: 数十年にわたる研究の蓄積があり、効果は十分に証明されています。
- メリット:
- 全ての栄養素をバランスよく摂取できる
- 食品の選択肢が広い
- 長期継続しやすい
- デメリット:
- カロリー計算が煩雑
- 空腹感を感じやすい場合がある
- 全てのカロリーが同等と考える単純な計算には限界も
私の外来でも、基礎代謝量から算出した適切なカロリー設定で、多くの患者さんが成功されています。例えば、45歳の女性会社員Aさんは、1日1400キロカロリーに調整し、半年間で10kg減量に成功しました。
糖質制限の仕組みと特徴
糖質制限は、炭水化物(糖質)の摂取量を制限する方法です。典型的な低糖質食では、1日の総カロリーの20%以下を糖質から摂取します。
- 科学的根拠: 過去20年ほどで研究が急増し、短期的な効果は十分に証明されています。
- メリット:
- 初期の体重減少が比較的速い
- インスリン分泌の抑制により、脂肪分解が促進される
- 満腹感を得やすい(タンパク質と脂質の摂取増加による)
- 血糖値の変動が少なく、糖尿病予備群の方に有効な場合も
- デメリット:
- 食物繊維摂取が不足する可能性
- 社会生活での制約(外食や会食での制限)
- 極端な制限は継続が難しい
- 長期的な安全性についてはまだ研究途上
38歳の男性会社員Bさんは、糖質制限(1日100g以下)で3か月で8kg減量され、HbA1c(血糖値の指標)も改善されました。
最新の研究からわかること
興味深いことに、最近の大規模研究では、12ヶ月以上の長期で見ると、どちらの方法も同程度の減量効果があることがわかってきました。
例えば2018年のJAMA誌に発表された研究では、低脂肪食と低糖質食を1年間比較したところ、両者の体重減少に有意差はなく、どちらも平均5〜6kgの減量効果があったとのことです。
現実的なアプローチ:あなたに合った方法は?
ダイエット法選びで最も重要なのは「継続できるか」という点です。どんなに効果的な方法でも、続けられなければ意味がありません。
以下のような観点から自分に合った方法を検討してみましょう:
- 生活スタイル: 外食が多い方は厳格な糖質制限は難しいかもしれません
- 嗜好: 甘いものより肉や脂っこいものが好きな方は糖質制限の方が合うかも
- 過去の経験: これまで試した方法で、続きやすかったものはどれか
- 健康状態: 糖尿病や脂質異常症など、既往歴によって向き不向きがある
「どちらか一方」ではなく、両方のいいとこ取りをする中間的アプローチも効果的です。例えば:
- 総カロリーを適度に制限しながら(約20%減)
- 炭水化物の質を見直し(白米→玄米、白パン→全粒粉パンなど)
- 極端な糖質制限はせず、砂糖入り飲料や菓子類を控える
このバランス型アプローチで、50歳の女性教師Cさんは1年かけて12kg減量し、3年経った今も体重を維持されています。
「絶対的に正しい方法」はなく、その人に合った方法が「最良の方法」なのです。次の項では、どのようなダイエット法を選ぶにしても重要な「栄養素バランス」について解説します。
健康的な減量に必要な栄養素バランス
「ダイエット中でも栄養は大丈夫でしょうか?」
これは非常に重要な質問です。体重を減らすことだけに注目すると、栄養不足に陥るリスクがあります。健康的な減量では、カロリー制限をしながらも必要な栄養素はしっかり摂ることが大切です。
PFCバランスとは
食事の栄養バランスを示す指標として「PFCバランス」があります。これは、Protein(タンパク質)、Fat(脂質)、Carbohydrate(炭水化物)の頭文字を取ったものです。
標準的には以下の割合が推奨されています:
- タンパク質:13〜20%
- 脂質:20〜30%
- 炭水化物:50〜65%
しかし、減量中はこれを少し調整するとより効果的です。具体的に見ていきましょう。
タンパク質:減量成功の鍵
「ダイエット中こそタンパク質が重要」と私はいつも患者さんに伝えています。その理由はいくつかあります:
- 筋肉量の維持: カロリー制限中、タンパク質が不足すると筋肉が分解されやすくなります。筋肉が減ると基礎代謝も下がり、減量がより難しくなります。
- 満腹感の持続: タンパク質は他の栄養素より満腹感が長続きします。ある研究では、朝食のタンパク質を増やした群は、そうでない群と比べて夕方までの間食が30%減少したというデータもあります。
- 食事誘発性熱産生: タンパク質は消化・吸収に多くのエネルギーを使います(摂取カロリーの約25-30%)。対して、炭水化物は約6-8%、脂質は約2-3%程度です。
ダイエット中の推奨摂取量は、体重1kgあたり約1.5〜2.0gです。例えば体重60kgの方なら、1日に90〜120gのタンパク質が目安になります。
具体的な食品例:
- 鶏むね肉100g = 約23gのタンパク質
- 木綿豆腐1丁 = 約20gのタンパク質
- 卵1個 = 約6gのタンパク質
- 牛乳200ml = 約6gのタンパク質
「タンパク質を意識するようになってから、空腹感に悩まされなくなりました」と話す32歳のDさん。半年で7kg減量に成功されています。
脂質:量より質を重視
脂質は1gあたり9kcalと高カロリーなため、ダイエット中は制限しがちですが、完全に避けるのは逆効果です。重要なのは「質」です:
- 必須脂肪酸: 体内で合成できないオメガ3・オメガ6脂肪酸は、健康維持に必須です。
- 脂溶性ビタミン: ビタミンA、D、E、Kは脂質がないと吸収されません。
- 良質な脂質源: オリーブオイル、アボカド、ナッツ類、青魚などに含まれる不飽和脂肪酸を優先しましょう。
- 避けたい脂質: トランス脂肪酸(一部の菓子パンやスナック菓子に含まれる)や過剰な飽和脂肪酸(動物性脂肪に多い)
ダイエット中は総カロリーの20〜30%程度を脂質から摂るのが理想的です。
炭水化物:量と質の両面から見直す
炭水化物についても、単に「減らす」だけでなく「質」に注目することが大切です:
- 複合炭水化物を選ぶ: 白米→玄米、白パン→全粒粉パン、じゃがいも→さつまいもなど、食物繊維が豊富でGI値(血糖上昇指数)の低い食品を選びましょう。
- 添加糖を減らす: 砂糖入り飲料、菓子類、甘いソースなどに含まれる「添加糖」を減らすことが効果的です。
- 食物繊維を増やす: 野菜、豆類、海藻などから十分な食物繊維を摂ると、満腹感が高まり、血糖値の急上昇も抑えられます。
糖質制限をしない場合でも、炭水化物は総カロリーの45〜55%程度に抑えるのが減量中の目安です。
ダイエットタイプ別のPFCバランス例
どのようなダイエット法を選ぶかによって、理想的なPFCバランスは異なります:
- バランス型減量食:
- タンパク質 25%
- 脂質 25%
- 炭水化物 50%
- 中程度の糖質制限:
- タンパク質 30%
- 脂質 35%
- 炭水化物 35%
- 低糖質食:
- タンパク質 35%
- 脂質 45%
- 炭水化物 20%
「最初はカロリーだけ気にしていたのですが、先生のアドバイスでタンパク質と食物繊維を増やしたら、同じカロリーでも満足感が全然違いました」
こう話すのは、40代のEさん。PFCバランスを見直すことで、1300kcalという比較的緩やかなカロリー制限でも着実に減量できたそうです。
栄養バランスを整えることは、単に健康維持のためだけでなく、ダイエットの成功率を高める重要な要素なのです。次の項では、近年注目されている「時間で食事を管理する方法」について解説します。
時間制限食・間欠的断食の可能性
「食べる内容だけでなく、食べる時間も重要なのですか?」
近年の研究で、「何を食べるか」だけでなく「いつ食べるか」も健康と体重に大きく影響することがわかってきました。時間制限食(タイムレストリクテッドイーティング)や間欠的断食(インターミッテントファスティング)は、その代表的な方法です。
時間栄養学の基本概念
私たちの体には「体内時計」があり、ホルモン分泌や代謝活性が24時間周期で変動しています。例えば、インスリン感受性(血糖を下げる働き)は朝が最も高く、夜になるほど低下します。
つまり、同じものを食べても、朝と夜では体への影響が異なるのです。これが「時間栄養学」の基本概念です。
主な時間制限食の方法
- 16:8法
- 1日16時間は断食し、8時間の間に食事をとる方法
- 一般的には正午から午後8時までの間に食事をとる
- 最も実践しやすく研究データも豊富
- 5:2法
- 週5日は通常通り食事し、週2日は大幅にカロリーを制限(女性は500kcal、男性は600kcal程度)
- 連続しない2日を選ぶことがポイント
- 隔日断食
- 1日おきに通常食と低カロリー食(または完全断食)を繰り返す
- 効果は高いが継続性に課題あり
「41歳女性のFさんは、朝食を抜いていることに罪悪感があると話していました。しかし彼女の場合、朝は自然と食欲がなく、正午から午後8時の間の2食で十分満足していたため、16:8法を公式に取り入れることをアドバイスしました。半年で5kg減量し、血液検査値も改善されています」
科学的根拠:なぜ効果があるのか?
時間制限食・間欠的断食が減量や健康改善に効果がある理由はいくつかあります:
- カロリー摂取の自然な減少
- 食事時間を制限すると、自然と総カロリー摂取量が減少する傾向があります
- 特に夜間の無意識な間食が減少します
- インスリンレベルの安定化
- 断食期間中はインスリン値が低下し、脂肪燃焼モードに入りやすくなります
- 血糖値の変動が少なくなることで、空腹感も安定します
- オートファジーの促進
- 12時間以上の断食で「オートファジー」という細胞の自己浄化機能が活性化
- 2016年にノーベル医学生理学賞を受賞したテーマです
- 体内時計のリセット
- 食事時間を規則的にすることで体内時計が整い、代謝機能が改善します
最新の研究結果から
JAMAネットワークオープン誌に2020年に発表された研究では、肥満者を対象に12週間の16:8法を実施した結果、対照群と比較して体重が約3%減少し、血圧も低下したことが報告されています。
また、Cell Metabolism誌の研究では、8週間の時間制限食により、内臓脂肪の有意な減少とインスリン感受性の改善が確認されています。
実践する際の注意点
時間制限食・間欠的断食はすべての人に適しているわけではありません:
- 健康状態のチェック: 糖尿病、低血糖症、妊婦、成長期の子ども、高齢者などは医師に相談してから
- 水分摂取の維持: 断食中も十分な水分(水、お茶など)を摂取することが重要
- 段階的な導入: いきなり長時間の断食は避け、徐々に時間を延ばしていく
- 栄養バランスの確保: 食事時間が短くても、必要な栄養素をバランスよく摂ることが大切
「忙しくて朝食を準備する時間がない」「夕食後の間食が止められない」という方には、特に取り入れやすい方法かもしれません。
ただし、無理な断食や極端な制限は逆効果です。自分の生活リズムに合った方法を見つけることが大切です。次の項では、食習慣の効果的な見直し方について解説します。
食習慣の効果的な見直し方
「何を食べるかより、どう食べるかが重要なのですね」
これは私の外来でよく伝えていることです。食習慣、つまり「食べ方」の改善は、特別な食事制限をしなくても効果が表れる場合が多く、長期的な成功につながります。
ゆっくり食べることの科学的効果
早食いは肥満と強く関連していることが複数の研究で示されています。ある日本の研究では、早食いの人は標準的な食べる速さの人と比べて、肥満リスクが約2倍高いという結果も出ています。
なぜゆっくり食べることが重要なのでしょうか?
- 満腹ホルモンのタイミング
- 食事を始めてから約20分で満腹ホルモン(レプチンやコレシストキニンなど)が分泌されます
- 早食いだと、これらのホルモンが分泌される前に必要以上の量を食べてしまいます
- 咀嚼回数の増加
- よく噛むことで満腹中枢が刺激されます
- 一口30回以上噛むことで、摂取カロリーが約10%減少するという研究結果もあります
- 食事の満足感向上
- 味わって食べることで少量でも満足感が高まります
- 食後の追加摂取(おかわりや間食)が減少する傾向があります
「36歳の会社員Gさんは、昼食を10分で済ませていましたが、最低20分かけて食べることに変更しただけで、自然と食べる量が減り、3ヶ月で3kg減量できました」
実践法:ゆっくり食べるための工夫
- 食事時間を最低20分確保する
- 一口ごとに箸やフォークを置く
- 十分に咀嚼してから次の一口を取る
- 食事中に会話を楽しむ(一人の場合は咀嚼に集中)
- タイマーをセットして時間を意識する
間食管理の重要性
間食(スナッキング)は、気づかないうちに総カロリー摂取量を増加させ、ダイエットの障壁となることがあります。
ある研究では、間食の頻度が高い人は、そうでない人と比べて体重増加のリスクが約1.6倍高いという結果も出ています。
しかし、間食を完全に禁止するのは現実的ではなく、かえって反動で過食につながることも。大切なのは「賢い間食戦略」です。
間食管理の3つのポイント
- 計画的な間食
- 間食を禁止するのではなく、1日のカロリー計画に組み込む
- 空腹感が強くなる時間帯を予測して準備
- 「間食しない」より「何を間食するか」を考える
- 間食の質の向上
- 高タンパク・高繊維の間食を選ぶ
- おすすめ例:
- ゆで卵1個(約70kcal、タンパク質6g)
- プレーンヨーグルト小鉢(約100kcal、タンパク質6g)
- ナッツ類少量(アーモンド10粒程度で約70kcal)
- 野菜スティックと少量の低脂肪ディップ
- 加工度の高いスナック(特に甘いお菓子や塩辛いスナック)を避ける
- 間食の食べ方
- 小分けにして取り分ける(パッケージから直接食べない)
- 意識的に味わって食べる(「ながら食い」を避ける)
- キッチンや食卓に座って食べる(テレビの前やデスクでの食事を避ける)
「45歳のHさんは、夕食後のお菓子をやめられないと悩んでいましたが、就寝前のハーブティーとゆっくりお風呂に入る習慣を作ることで、甘いものへの欲求が自然と減りました」
マインドフルイーティングの実践
食事への意識を高める「マインドフルイーティング」も効果的です:
- 食事に集中する
- テレビやスマートフォンを見ながらの食事を避ける
- 食事の色、香り、味、食感を意識的に味わう
- 空腹と満腹のサインを認識する
- 食べる前に空腹度を0-10で評価する習慣をつける
- 「お腹が80%程度満たされた」時点で食事を終える
- 感情的な食べ過ぎへの対策
- ストレスや退屈、孤独などの感情と食欲の関連に気づく
- 食べる前に「本当に空腹か?」と自問する習慣
- 食べる以外のストレス解消法を見つける(短い散歩、深呼吸、入浴など)
ある研究では、マインドフルイーティングを取り入れたグループは、そうでないグループと比較して6か月間で約3kg多く減量したという結果も出ています。
「小さな習慣変化が大きな違いを生む」―これが食習慣改善の真髄です。次の項では、太りにくい体を作る食事のタイミングについて解説します。
太りにくい体を作る食事のタイミング
「同じものを食べても、食べるタイミングで太りやすさが変わるのですか?」
はい、その通りです。近年の「時間栄養学(クロノニュートリション)」の研究から、同じ食事でも摂取するタイミングによって、代謝への影響が異なることがわかってきました。
体内時計と代謝の深い関係
私たちの体には「体内時計(サーカディアンリズム)」があり、ホルモン分泌や代謝活性などを24時間周期で調整しています。
例えば、インスリン(血糖を下げるホルモン)の感受性は朝に最も高く、夜になるほど低下します。これは、同じ食事でも朝と夜では体への影響が異なることを意味します。
朝食の重要性:科学的根拠
「朝食を抜くと太る」という言葉、実は科学的根拠があります:
- 代謝活性化効果
- 朝食摂取により基礎代謝が活性化されます
- 食事誘発性熱産生(食事の消化・吸収に使われるエネルギー)が朝は高い傾向があります
- ある研究では、同じカロリーの食事でも、朝に摂取した場合は夕方に比べて約2.5倍のカロリーが消費されたというデータも
- 食欲コントロール効果
- 朝食を抜くと、昼食時に過食しやすくなります
- 特に高タンパク質の朝食は、一日を通して食欲調節ホルモンのバランスを整えます
- 米国の大規模調査では、定期的に朝食を摂る人は肥満リスクが約30%低いという結果も
「28歳の女性Iさんは朝食を抜いていましたが、高タンパクの簡単な朝食(ゆで卵とヨーグルト)を取り入れたところ、昼食の量が自然と減り、3ヶ月で4kg減量できました」
夕食のタイミングが体重に与える影響
夕食の時間も体重管理に重要な影響を与えます:
- 就寝前の食事は要注意
- 就寝前3時間以内の食事は、脂肪として蓄積されやすくなります
- 夜10時以降の食事は、インスリン感受性の低下により、代謝効率が悪くなります
- スペインの研究では、夕食が遅い群(午後10時以降)は、早い群(午後8時前)と比べて減量効果が約25%低かったというデータも
- 夜間の代謝低下
- 夜間は基礎代謝が約10%低下します
- メラトニン(睡眠ホルモン)分泌後はインスリン感受性が低下します
- 夜間は満腹感を得にくい(レプチン感受性の低下)傾向があります
「残業が多い52歳の会社員Jさんは、夜9時以降の夕食が習慣でしたが、オフィスに軽食を持参し、午後7時までに何か食べるよう変更しただけで、2ヶ月で3kg減量されました」
食事間隔の最適化
- 適切な食事間隔
- 食事間には最低3-4時間の間隔を確保するのが理想的です
- インスリンが完全に低下するための時間が必要です
- 「少量頻回食」(1日5-6回の食事)は必ずしも代謝向上につながらないことが最近の研究でわかってきました
- むしろ、食事回数が多いと、インスリンが常に分泌され、脂肪燃焼モードに入りにくくなります
- 最適な食事回数
- 個人差はありますが、多くの研究では1日3回の規則的な食事が推奨されています
- 生活リズムに合わせた一貫した食事パターンが重要です
- どうしても間食が必要な場合は、午前中に摂るのが理想的です
「43歳の主婦Kさんは、小まめに食べる方が良いと思い、1日6回食べていましたが、3食に整理し、間食を減らしたところ、血糖値の変動が少なくなり、2ヶ月で2.5kg減量されました」
夜間の絶食時間を確保する
時間制限食の考え方を取り入れ、夜間の絶食時間を確保することは体重管理に効果的です:
- 12-14時間の絶食時間
- 例:夜8時の夕食後、朝8-10時まで絶食
- オートファジー(細胞の自己浄化機能)が促進されます
- 脂肪燃焼モードへの移行が促進されます
- 実践法
- 夕食後の飲み物は水、お茶、ノンカフェイン飲料に限定
- 朝食時間をなるべく一定に保つ
- 週末も平日と同様の食事スケジュールを維持する努力をする
個人の生活リズムに合わせた最適化
食事のタイミングを考える際、最も大切なのは「自分の生活リズムに合っているか」という点です:
- 朝型の人: 朝食をしっかり摂り、夕食は軽めにするのが理想的
- 夜型の人: 無理に早朝から食べるのではなく、起床後2-3時間以内に最初の食事を摂る
- シフトワーカー: 勤務スケジュールに合わせた規則的な食事パターンを作る
「ある看護師のLさんは夜勤が多く、食事時間が不規則でした。通常のアドバイスは合わないため、勤務パターン別の食事計画を一緒に立てました。起床後の最初の食事をメインにし、勤務中の食事は軽めにするというパターンが効果的で、半年かけて5kg減量されました」
食事のタイミングを最適化することで、同じカロリー摂取量でも体脂肪の蓄積を抑制できる可能性があります。個人の生活リズムに合わせつつ、体内時計と調和した食事パターンを確立することが、太りにくい体づくりの鍵となります。
第2章のまとめ:科学的ダイエットの5つの原則
これまで解説してきた内容から、科学的なダイエットの基本原則をまとめると:
- エネルギー収支を管理する
- カロリー制限と糖質制限、どちらも効果的
- 自分の生活スタイルに合った方法を選ぶ
- 極端な制限より持続可能な方法を優先
- 栄養バランスを整える
- タンパク質を十分摂取する(体重1kgあたり1.5-2g)
- 良質な脂質を適量摂る
- 炭水化物は量と質の両面から見直す
- 食べるタイミングを意識する
- 朝食を大切にする
- 夕食は早めに済ませる
- 夜間の絶食時間を確保する
- 食べ方を改善する
- ゆっくり時間をかけて食べる
- 間食を計画的に管理する
- マインドフル(意識的)に食べる
- 個人差を尊重する
- 自分の体質、生活リズム、嗜好に合った方法を選ぶ
- 「万人に効く魔法の方法」はない
- 継続できる方法こそが最良の方法
次章では、具体的な食事内容や、おすすめの食材、調理法について詳しく解説します。
監修
鎌形博展 株式会社EN 代表取締役兼CEO、医療法人社団季邦会 理事長
専門科目 救急・地域医療
所属・資格
- 日本救急医学会
- 日本災害医学会所属
- 社会医学系専門医指導医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 国際緊急援助隊・日本災害医学会コーディネーションサポートチーム
- ICLSプロバイダー(救命救急対応)
- ABLSプロバイダー(熱傷初期対応)
- Emergo Train System シニアインストラクター(災害医療訓練企画・運営)
- FCCSプロバイダー(集中治療対応)
- MCLSプロバイダー(多数傷病者対応)
研究実績
- 災害医療救護訓練の科学的解析に基づく都市減災コミュニティの創造に関する研究開発 佐々木 亮,武田 宗和,内田 康太郎,上杉 泰隆,鎌形 博展,川島 理恵,黒嶋 智美,江川 香奈,依田 育士,太田 祥一 救急医学 = The Japanese journal of acute medicine 41 (1), 107-112, 2017-01
- 基礎自治体による互助を活用した災害時要援護者対策 : Edutainment・Medutainmentで創る地域コミュニティの力 鎌形博展, 中村洋 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 修士論文 2016
メディア出演
- フジテレビ 『イット』『めざまし8』
- 共同通信
- メディカルジャパン など多数
SNSメディア
- Youtube Dr.鎌形の正しい医療ナビ https://www.youtube.com/@Dr.kamagata
- X(twitter) https://x.com/Hiro_MD_MBA
- 血圧の学校 https://med-pro.jp/media/htn/
関連リンク
- 株式会社EN https://www.med-pro.jp/en/
- 医療法人社団季邦会 https://wellness.or.jp/kihokai/
- 街のクリニック立川・村山 https://www.tamagawa-josui.com/
- 街のクリニック日野・八王子 https://www.machino-clinic.com/
- びやじま内科医院 大島駅前 https://www.clinic-ojima.com/