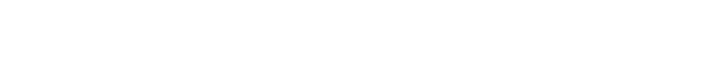疲労感の原因と対処法
こんにちは。高血圧といびきの内科 神保町駅前 院長の山須田です。
「なんだか疲れが取れない」「朝起きても疲れが抜けない」
そんなお悩みを抱える方は少なくありません。
加齢や忙しさのせいだけでなく、隠れた病気や生活習慣が関係している場合もあります。今回は疲労感の原因と対処法について、わかりやすく解説します。
1. 疲労感の原因
疲労感の背景には、以下のような疾患・原因が隠れていることがあります。
(1) 器質的疾患
・内分泌…甲状腺機能低下症、副腎不全、糖尿病、更年期障害
・心疾患…心不全、不整脈
・耳鼻科疾患…慢性咽頭炎、アレルギー性鼻炎(鼻閉)
・呼吸器疾患…喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群
・腎疾患…慢性腎臓病
・感染症…慢性肝炎、結核、感染性心内膜炎、HIV感染、伝染性単核球症
・膠原病…SLE、多発性筋炎/皮膚筋炎、シェーグレン症候群、関節リウマチ、血管炎
・血液疾患…鉄欠乏性貧血、悪性貧血、白血病、悪性リンパ腫
・神経筋疾患…多発性硬化症、筋ジストロフィー、パーキンソン病、重症筋無力症等
・その他…パーキンソン病、悪性腫瘍
主に血液検査でスクリーニングを行います。また、睡眠時無呼吸症候群は有病率が高いので、いびきや高血圧がある方には簡易検査をおすすめしています。
(2) 精神的要因
うつ病、不安障害、睡眠障害などが疲労感の背景にある場合があります。
(3) 機能性疾患
基礎疾患が検査で見つからず、休息で改善しない重度の疲労が6か月以上続く場合は慢性疲労症候群(ME/CFS)の可能性も考えられます。
(4) 薬の副作用
β遮断薬、抗がん剤、抗精神病薬、第一世代抗ヒスタミン薬、利尿薬などが疲労感を引き起こすことがあります。
(5) 生活習慣
睡眠不足、運動不足、飲酒、喫煙、カフェインや糖質の過量摂取、長時間のPC作業(VDT症候群)なども疲労感の原因になります。
どう対処すればよいか
原因となる病気があれば、その治療が第一です。その上で、
- 十分な睡眠(7時間程度)
- ストレッチや深呼吸でリラックス
- 適度な運動
などの生活習慣改善が大切です。
また、疲労回復を助ける栄養素として以下が知られています。
- イミダペプチド(鶏むね肉、カツオ)
- γオリザノール(米油、胚芽)
- ケルセチン(玉ねぎ、リンゴ)
- ビタミンB群
体内の炎症性サイトカインを抑え、内分泌機能を正常化し、十分な酸素と栄養を全身に運搬することが疲労回復において重要です。
2. 東洋医学から見た疲労感
東洋医学では、気血水・五臓のバランスを整えることが疲労感の回復につながると考えます。
- 気虚(元気が出ない、風邪をひきやすい):補中益気湯、六君子湯など
- 気滞(イライラ、不安、喉のつかえ):半夏厚朴湯、加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蛎湯など
- 血虚(貧血、立ちくらみ):人参養栄湯、当帰芍薬散など
- 陰虚(寝汗、口渇、皮膚乾燥):六味丸、八味地黄丸など
風邪の後に疲れが続く場合には小柴胡湯、柴胡桂枝湯、補中益気湯で炎症を鎮めて体力回復を図ることがあります。
***
疲労感は「年齢や忙しさのせい」と思われがちですが、病気のサインであることも少なくありません。
「なんだか疲れが取れない」と感じたら、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
<参考文献>
『疲労とはなにか』近藤一博著 講談社ブルーバックス