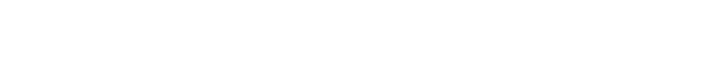肥満症と生活習慣病リスク
肥満と肥満症
肥満は、日本ではBMIが25以上で判定されます。
一方、肥満症はBMIが25以上に加えて、糖代謝異常や脂質異常症、高血圧など肥満に起因・関連する健康障害を合併している、または内臓脂肪の過剰蓄積(将来的な合併が高い)があるため医学的に減量を要する病態を指します。腹部CTで内臓脂肪面積(VFA)が100 cm²以上、あるいはウエスト周囲長(へその高さ)が男性85 cm、女性90 cm以上は内臓脂肪過剰の指標で、肥満症として扱います(VFA≥100 cm²相当)。
日本における肥満の割合
直近の国民健康・栄養調査(令和5年)では、肥満者(BMI≥25)の割合は男性31.5%、女性21.1%でした。男性は平成25年から令和元年の間に有意に増加し、その後は横ばい、女性はこの10年間で有意な増減はみられていません。
メタボリックシンドロームに関しては、令和元年調査の集計で20歳以上男性の28.2%、女性の10.3%が「強く疑われる」、さらに男性23.8%、女性7.2%が予備群と報告されています。年齢を40~74歳に絞ると、男性では約2人に1人が該当または予備群という規模です。
メタボリックシンドローム
腹部肥満(男性85 cm/女性90 cm以上※)を必須とし、次の3項目中2つ以上の該当で診断します。
・脂質:TG(中性脂肪)≥150 mg/dL または HDL-C<40 mg/dL
・血圧:収縮期≥130 mmHg または 拡張期≥85 mmHg
・血糖:空腹時血糖≥110 mg/dL
※腹囲カットオフは、内臓脂肪面積100 cm²に対応する値から導かれています。
これらの複数の因子が重なることで動脈硬化リスクは相乗的に上昇します。
糖尿病・高血圧・脂質異常症との関係
BMIが上がるほど2型糖尿病の発症リスクは直線的に上昇します。アジア人は欧米人に比してインスリン分泌能が低く、BMIが25前後でも発症リスクが上がるため、日本人では比較的軽度の体重増加でも糖尿病を招きやすいことが分かっています。
その他肥満では中性脂肪上昇、HDL低下傾向がみられます。交感神経亢進や内分泌系の変化により、血圧上昇を来します。
内臓脂肪貯蓄は、TNF-α・アンギオテンシノーゲン・PAI-1上昇によるインスリン抵抗性・高血圧・血栓傾向を来すほか、アディポネクチン低下によるインスリン感受性低下も来します。
肥満症・メタボリックシンドロームの対処法
ガイドライン的には、肥満症では現体重の3%減、高度肥満症(BMI≧35)では5~10%減を初期目標とします。血糖・血圧・脂質・肝機能・睡眠時無呼吸などを複合的に検査し、食事・運動療法に加え必要に応じて薬物治療を行います。
摂取カロリー制限(推定消費カロリーから300~500kcal/日ほど減らす)・PFCバランス(糖質5:脂質3:タンパク質2)・有酸素運動週150分を心がけます。
生活介入で十分な効果が得られない肥満症に対しては、GLP-1受容体作動薬などの薬物療法を検討する場合があります。高度肥満で重篤な合併症を伴う場合は、減量手術(スリーブ状胃切除術)が行われるケースもあります。