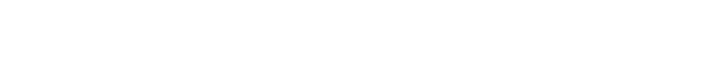摂食コントロールの仕組みと肥満
私たちの食欲は、大きく分けて「恒常性調節」「報酬系調節」の2つの仕組みによってコントロールされています。
恒常性調節とは、エネルギーの過不足に応じて空腹感または満腹感を調節する仕組みです。
報酬系調節とは、美味しいものほど刺激が強く空腹感をもたらす仕組みです。
健常者では、この2者がバランスよく機能しています。
ところが肥満者では、バランスが崩れ制御ができなくなっていることが分かっています。
今回は、この仕組みの概要を説明します。
恒常性調節
脳の視床下部弓状核にある「POMCニューロン」と「NPY/AgRPニューロン」が食欲を制御しています。POMCニューロンは食欲を抑える神経、NPY/AgRPニューロンは食欲を促す神経です。
この2者は互いを抑制しあう関係です。レプチンやインスリン等のホルモンはこれらの神経に作用して食欲をコントロールしています。
報酬系調節
中脳の腹側被蓋野(VTA)-側坐核(NAc)にある報酬系ドーパミン回路による食欲のコントロールです。
甘味や高脂肪食などは、このドーパミン回路を刺激して快感をもたらします。脳はこの報酬系刺激を学習するので、美味しいものを食べるのを理性で抑えるのが困難になってきます。
ホルモンによる調節
脂肪細胞から分泌されるレプチンは、POMCニューロン活性、NPY/AgRPニューロン抑制により食欲を抑えます。膵臓β細胞から分泌されるインスリンもPOMCニューロン活性により食欲を抑えます。これは、貯蓄エネルギーあるいは血糖が十分ある状態ではこれらのホルモン濃度が上昇し、食欲を抑えるという仕組みです。
他にも、消化管由来のペプチドYY (PYY)、膵ポリペプチド (PP)、グルカゴン様ペプチド-1 (GLP-1) 及びオキシントモジュリン (OXM)などのホルモンも食欲を抑える働きがあります。
一方、胃から分泌されるグレリンはNPY/AgRPニューロン活性により食欲を促進する働きを有します。睡眠不足状態はグレリンの血中濃度を上昇させ過食の原因になることが判っています。
レプチン抵抗性
レプチンが正しく機能していれば、エネルギー充足状態では食欲が抑制されるはずです。ところが、肥満者ではレプチンが正しく機能しておらず、恒常性調節が破綻してしまいます。この状態をレプチン抵抗性と言います。
肥満者では血液脊髄液関門の通過障害、星状膠細胞の増殖による受容体への結合低下、飽和脂肪酸により誘導される炎症性サイトカインによる阻害など複数の原因により、レプチンの作用が低下しています。
まとめ
肥満の背景には、レプチン抵抗性による悪循環、食生活の乱れによる報酬系調節の破綻、睡眠不足・ストレス・高脂肪食などによるレプチン・グレリンバランスの破綻など複数の要因が関係しています。 規則正しい生活リズムと食習慣の見直しが、脳の摂食調節機構を整え