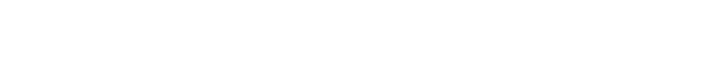安定狭心症(労作性狭心症)について
こんにちは、高血圧といびきの内科神保町駅前 院長の山須田です。
当院には高血圧でお悩みの患者様が数多く来院されますが、その中で時々ご相談いただく症状の一つに「胸痛」があります。
当院は予防医療を中心としたクリニックですので、突然の胸痛発作は急性冠症候群、大動脈解離、肺塞栓症、気胸など迅速な治療を要する疾患を念頭に急性期病院に受診をお願いしています。しかし、問診中に「数分程度で治まる胸痛が数年前からあって…」とおっしゃる患者様は稀ではありません。
ここでは、そのような症状を呈する安定狭心症(労作性狭心症)について解説いたします。
安定狭心症とは
安定狭心症(stable angina)とは、冠動脈疾患(coronary artery disease, CAD)のなかの一つです。冠動脈の内腔がアテローム性動脈硬化や痙攣などにより慢性的に狭窄し、心筋に必要な酸素が足りなくなり胸痛や胸部圧迫感を生じるもので、運動や心臓に負荷がかかった時など一定の条件下で症状が出るものを特に安定狭心症と呼びます。
冠動脈がプラーク破綻やそれに伴う血栓形成により不可逆的に閉塞してしまった状態(急性心筋梗塞)、閉塞しかけているもの(不安定狭心症)は急性冠症候群(ACS)と呼ばれ、症状が続く場合直ちに救急要請、治療が必要となります。
冠動脈疾患(coronary artery disease, CAD)全体の中の分類としては、CAD全体は急性冠症候群(ACS)と慢性冠症候群(CCS)に大別され、そのCCSサブタイプ(下記)のうち安定狭心症はCCSⅠとCCSⅣに相当します。
<CCSサブタイプ>
| CCSⅠ:”安定型”狭心症の症状かつ/または呼吸苦を有するCADおよびCAD疑いの患者 CCSⅡ:新規発症の心不全または左室機能障害を有するCAD疑いの患者 CCSⅢ:ACS発症後1年未満の安定している患者や最近血行再建を受けた患者 CCSⅣ:CADの診断または血行再建により1年以上経った無症候性または症候性の患者 CCSⅤ:冠攣縮または微小血管障害を伴う狭心症患者 CCSⅥ:スクリーニング検査でCADが発見された無症候性の患者 |
狭心症には他にも冠攣縮性狭心症(Variant angina)とよばれるタイプがあります(上記表のCCSⅤ)。
異型狭心症ともよばれ、冠動脈の一時的な痙攣によって血流が遮断されるもので、通常は安静時、特に夜間や早朝に発作が起こります。発作時に一過性のST上昇を伴うが冠動脈に明らかな狭窄が見られないものです。
狭心症の症状
典型的な症状は、前胸部の圧迫感・絞扼感です。痛みは通常数分間持続し、労作(歩行や階段昇降)・温度差・精神的ストレスによって誘発されます。
痛みはしばしば左肩、左腕、顎、背中、上腹部に放散することがあります。また、疼痛としてではなく違和感や圧迫感として出現する場合もあります。特に高齢者や糖尿病患者では無症候性の事があり注意を要します。
随伴症状として、動悸、冷汗、めまい、吐き気、倦怠感が出現することもあります。
狭心症のリスク因子
最も重要なのは高血圧・高LDLコレステロール・糖尿病です。これらの疾患は血管内皮を損傷し動脈硬化を進行させる大きな要因です。
喫煙は動脈硬化だけではなく、冠動脈攣縮を誘発しリスク因子となります。
肥満・運動不足・ストレス・過労・過剰なアルコールはメタボリックシンドロームとしてリスクを高めます。
ほかにも、睡眠時無呼吸症候群・加齢・男性または閉経後女性・冠動脈疾患の家族歴などがリスク因子に挙げられます。
安定狭心症の検査・診断
病歴、リスク因子、簡易検査(CXp、ECG、心エコー、採血)等でACSおよび胸痛を生じる他の疾患をできる限り除外します。後述の非侵襲的画像検査が必要かどうかは、検査前確率(pre-test probability, PTP)と臨床的尤度(clinical likelihood, CL)で判断します。
<狭心症の評価>
①胸骨下(または頸部、顎、肩、腕)の絞扼感または締め付けられるような痛み
②運動や精神的ストレスによる増悪
③安静もしくはニトログリセリンによる5分以内の症状緩和
上記①~③全てを満たすものは「心臓性胸痛」と呼び、典型的狭心症の症状です。
上記①~③のうち2つを満たすものは「心臓性胸痛疑い」で非典型的狭心症となります。
上記①~③のうち1つ以下しか満たさないものは「非心臓性胸痛」と呼びます。
「2019年欧州心臓病学会(ESC)ガイドラインによるPTPモデル」(下記表)でおおよその検査前確率を評価していきます。
| 心臓性胸痛 | 心臓性胸痛疑い | 非心臓性胸痛 | 呼吸困難 | |||||
| 年齢 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 30-39 | 3% | 5% | 4% | 3% | 1% | 1% | 0% | 3% |
| 40-49 | 22% | 10% | 10% | 6% | 3% | 2% | 12% | 3% |
| 50-59 | 32% | 13% | 17% | 6% | 11% | 3% | 20% | 9% |
| 60-69 | 44% | 16% | 26% | 11% | 22% | 6% | 27% | 14% |
| 70~ | 52% | 27% | 34% | 19% | 24% | 10% | 32% | 12% |
赤:非侵襲的検査が有効(PTP>15%) 黄:PTPとCLを総合して検査を考慮
これに、下記表の病歴や検査で確認した臨床的尤度(CL)を加味して非侵襲的画像検査をすべきか判断します。
| 病歴・既往歴 | 心血管疾患、poly-vascular diseaseの既往 脂質異常症・糖尿病・脳卒中・PAD・CKDなど 若年性CADの家族歴 喫煙 |
| 安静時ECG | 異常Q波、ST-T異常 |
| 安静時UCG | 左室壁運動異常 |
| 血液検査 | 脂質異常、高血糖・耐糖能異常 |
安定狭心症の画像検査・冠動脈造影
PTP&CLで低リスク(CADの可能性が5%未満)と判断した場合は、経過観察ないし冠動脈カルシウムスキャン(CAC)検討とします。
PTP&CLで中~高リスク(CADの可能性が5%以上)と判断した場合は、冠動脈CTを行います。冠動脈CTは陰性的中率が高く、閉塞性CADの可能性はほぼ除外できます。もし検査で冠動脈狭窄があると疑われた場合は、負荷イメージングで機能的検査(心筋虚血評価)を行います。検査で左主幹部(LMCA)/LMCA相当病変(※)を示唆する所見を認めた場合は、負荷イメージングをせず冠動脈造影(CAG)を行うことがあります。
※…LMCA狭窄≧50%、LADとdominant LCxの近位部の有意狭窄、LADとdominant RCAの近位部の有意狭窄
負荷イメージングは、負荷心筋シンチグラフィや負荷心エコー等を行い、心筋虚血の評価を行います。可能な施設は限られますが、負荷イメージング以外にFFR-CTで冠動脈狭窄の程度を評価することもあります。
冠動脈造影(CAG)は、後述の至適薬物療法で症状が改善みられない場合や、ACSへの進展が予測される病態、LMCA/LMCA相当の病変、進行したCKD、心不全・左室機能不全を有する場合に行います。狭窄の部位およびFFR(fractional flow reserve)を算出します。FFR0.75未満は虚血あり、0.75-0.80はグレーゾーン、0.80より大きければ虚血は否定的と判断します。
安定狭心症の至適薬物療法
安定狭心症に対する基本的治療は指摘薬物療法(OMT)です。
症状緩和目的に短時間作用型の硝酸薬(ニトログリセリン、硝酸イソソルビド)、β遮断薬(メインテート等)、Ca拮抗薬(アムロジピン、コニール、アダラートCR等)を第一選択薬として使用します。長時間作用型の硝酸薬やニコランジル(シグマート)は第二選択薬となります。
心血管イベント予防目的として、ストロングスタチンを使用します(LDL-Cを開始時から50%以上低下、LDL-C目標70mg/dL未満)。
安定CADに対する低用量アスピリンは二次予防では基本適応ですが、一次予防に関しては評価が定まっておらず、出血リスクと心血管イベントリスクを考慮の上で使用を検討します。
血圧は若年者130/80mmHg未満、高齢者140/90mmHg以下を目標とします。
安定狭心症の冠血行再建術
通常FFR0.80以下が経皮的冠動脈インターベンション(percutaneous coronary intervention, PCI)の適応となります。PCI不適応例に対してはCABG(冠動脈バイパス術)が選択されます。
<参考文献>
2022年JCSガイドラインフォーカスアップデート版安定冠動脈疾患の診断と治療
2023年改訂版 冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン